No.5
医師の働き方改革について
医師の長時間労働は、大きな課題となっています。救急患者を頻回に受け入れる病院と、療養型病床や診療所では少し異なりますが、日本の医療は在宅重視に大きくかじを切っており、これからは在宅医療を担う診療所の医師の働き方も課題になると考えます。
厚生労働省の「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」は平成29年4月6日に報告書をまとめ、短時間労働や時差勤務の導入といった勤務体系の見直しや、偏在是正を目的とした外来医療提供体制の最適化、医師の業務を他職種に移管する「タスク・シフティング」の推進など、医療従事者の働き方について多岐にわたる提言を行いました。
検討会は、医療を取り巻く環境の変化や患者・住民のニーズの増大、多様化を踏まえ、今後目指すべき医療のあり方と、それを踏まえた医師や看護師等の働き方・確保のあり方について検討されており、特に労働時間のルールを医師も遵守すべきであるという強い意見が出てきたことが特徴的であります。
医師会の懇談会等において病院管理者からは「医師の残業時間を制限したら救急医療が担えない」「患者が受診に来ているのに、医師の超過勤務が上限を超えているので診察できないというのか!」「労働基準法を完璧に守ったら病院がつぶれる」などといった意見が多く聞かれます。
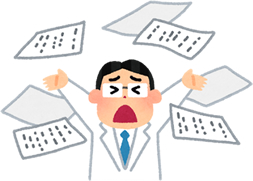 一方、労働基準監督官からは「では、医師は過労死してもいいのか」「そんな病院が医師確保できるのか」という反論があります。先般、新潟市民病院の研修医の自殺について、直前1カ月の残業時間が160時間を超えていたとして、新潟労働基準監督署が労災認定いたしました。 一方、労働基準監督官からは「では、医師は過労死してもいいのか」「そんな病院が医師確保できるのか」という反論があります。先般、新潟市民病院の研修医の自殺について、直前1カ月の残業時間が160時間を超えていたとして、新潟労働基準監督署が労災認定いたしました。
この問題は、主治医としての責任とともに、医師法は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている「応召義務」との関係が重要となります。
政府の働き方改革実現会議の実行計画によると、労働基準法などの改正によって時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられることになります。医師については改正法施行後5年間猶予されることとなりますが、具体的な解決策を考えていかなければなりません。
労働基準法上、医師が労働者であることは間違いありませんが、当の本人たちがその意識が薄く、管理者側もその意識に甘え、長時間労働が慢性的に行われている実態があります。
解決するためには医師不足が課題となりますが、これは医師数だけの問題ではなく、地域偏在やチーム医療の促進、患者の意識など様々な課題と連動しております。
いずれにしても、医師にとって働きやすい環境を整えることが病院運営を持続させるために必要であることは間違いないと考えます。
社会保険労務士 西尾 雅夫
|