No.4
DPC分析の活用について
今回は市販されているDPC分析ツールにおける活用例を紹介いたします。DPC分析ツールには様々なものがあり、それぞれの利点が異なる為、ユーザーの求めるものにより選択するツールが変わってくると思います。このうち、いくつかのDPC分析ツールにおいて装備されている機能のひとつが他院(同ツールのユーザーである病院)とのベンチマークが可能なことです。客観的な情報が加わることで、より精度の高い分析が可能となり、診療部への説得力も増します。
なお、特定のソフトを推奨するものではありませんので、あくまでDPC分析の例としてご参照下さい。
活用事例1:DPCと出来高の比較
DPCは実際の入院収入を表しますが、出来高はすべての医療行為を出来高の診療報酬点数表に基づいて積み上げた値であり、コストの概算として捉えることができます。
例えば、「DPC−出来高」の点数差異がマイナスとなる診療科は、診療が過剰気味で非効率である可能性が指摘されます。そこで、診療の中身を分析して“ムダ”がないか探して適正化するマネジメントが必要になります。
診療現場において常にDPC上有利な選択を行うことは難しいと思いますが、高額な医薬品、診療材料を使用する際は、自らの診療行為が包括部分に当たるのか、出来高で算定されるのか、病院の持ち出しになるのかどうかは診療サイドに理解していただく必要があります。
CTやMRIの撮影等、外来で行うべき行為を包括に含まれる入院期間中に実施することをルーティン化していた事例もあります。
逆に「DPC−出来高」の点数の値がプラスに大きい場合は、経済的な効果が高い診療であると推測できる一方、診療が薄い可能性もあります。安全性や質を担保する医療がきちんと行われているかどうか、データの精度が高いかどうかを確認する必要があります。
いずれにしても、一症例ずつ確認すると診断群分類の選択が適正でない場合もありますが、診療内容に踏み込む場合は現状を説明するために、視覚的にいかに見やすくするかがポイントになります。
医療の標準化を進める目的で導入されたDPC制度ですので、複数の症例において差がでているとすると、平均的な診療から逸脱しているという可能性もあり、その理由が適正であるのかを確認する必要があります。

活用事例2:DPCに対応するクリニカルパスの対応
診療報酬における「診断群分類ごとの入院期間」は全国のDPC 関連病院のデータを基に設定されています。従って、「入院期間Ⅱ」はDPC 病院の平均在院日数を表しており、この日数内で退院している患者の割合が多ければ、効率の良い診療が行われていると考えられます。これを踏まえて、DPC 病院の平均在院日数を意識したパスの作成・改訂を行うことができます。
また、新規のパス作成においては、平均在院日数だけでなく、抗生剤は術後何日まで使用されたか、ドレーンは術後何日で抜去されたか、術後何日で退院したか、どの検査がどのタイミングで何回行われたか、どの画像診断がどのタイミングで何回行われたかなど、診療プロセスも他医療機関とのベンチマークを実施することで、より効率的で質の高いパスを作成していくことが可能となります。
上記はあくまで一例ですが、DPC分析を事務部門のみの仕事とせず、医師・看護師等医療従事者を巻き込んでチームで取り組むことが最も重要です。
また、分析ソフトの使用に限らず、厚生労働省が公開するDPC統計データを使ってエクセルで分析することや、二次医療圏や医療機関別の疾患別患者像等の様々なデータがインターネット上で公開されており、それらを使って分析することも可能です。
病院経営については勿論のこと、地域医療構想を踏まえた病床再編の検討についても、DPCデータを有効活用し、自院のマネジメントに繋げていくことが重要であると考えます。
診療情報管理士 太田 如乃
|



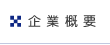

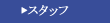

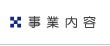
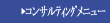

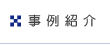




 個人情報の取扱について
個人情報の取扱について